家族が困らない!まんがでわかる得する相続
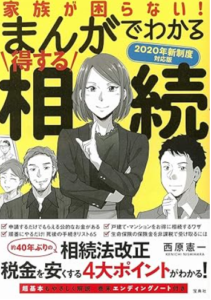
薄い本です★
しかし漫画というより丁寧な解説本です
相続というのは色々な側面がありながら
一気に時間勝負でことが進むようです
用意しないとパニックです
4章構成 と付録
項目だけでも読むべきです
税の絡みなど亡くなった方の納税をしなくてはなりません
65のチェックリストは
そういう抜け漏れを防止します
考えてみるとこういう本は
紙ベースで保管すべきなのかもしれません
第1章 手続きで得する
-老親・老配偶者が亡くなったら何をする
◆スムーズな死後の手続きは今から準備できる
◆基本は公的書類の提出。心配しすぎなくて大丈夫
◆ 費用は10万円程度。司法書士など専門家を使う手も
◆国や自治体は教えてくれない―「もらえる公的なお金」
◆ 生前に話し合わないと「相続」が「争続」に
◆「争族」になりがちなケースとは
◆そもそも財産を相続するのは誰か知っておこう
◆離婚や再婚を繰り返したケースに注意
◆死後にありがちなのは現金貧乏
第2章 得するもらい方 -基本的な相続の特例を活用しよう-
夫や妻の非課税分はいくらまで
◆子供の非課税分はいくらまで
◆基礎控除について理解しよう
◆相続税の最高税率は55%
◆実際の相続税の計算方法とは
◆預金をスムーズにもらう方法と注意点
◆生命保険の保険金を非課税で受け取る方法
◆生命保険を一時所得にする裏ワザ
◆車などの動産を相続する際の注意点
◆不動産の相続評価額はこうして計算する
◆不動産の相続のウィークポイント
◆小規模宅地等の特例で5000万円の土地が1000万円
◆自宅だけでなく店舗や工場、貸家も減額できる
◆事業用も含めて最大730㎡を80%減額
◆非上場株式や農地は納税猶予の特例をうまく使う
◆遺言書を書いておこう・書いてもらおう
第3章 得する9大改正【2020年版】
今回の相続税改正のポイントは
◆配偶者居住権の新設は子にも得するポイントが
◆自筆遺言書を法務局に保管してもらって「争」続回避
◆不動産の乗っ取り不可。遺留分の現金払いが可能に
◆故人を献身介護した赤の他人が報われる「特別の寄与制度」
◆凍結口座からでも最大150万円。これで金欠解消
◆配偶者に朗報、自宅を生前贈与して相続財産から除外
◆「争続」回避の切り札・遺言書を書くのがラクチンに
◆「抜けがけ」を許さない財産処分見直し
◆遺言書の効力見直し。不動産登記は早めに
第4章 生前贈与が最高に得
贈与と相続の違いとは
◆贈与にかかる贈与税の税率は
◆暦年贈与で年110万円まで非課税
◆連年贈与にならないよう注意
◆夫婦間の生前贈与で2000万円まで非課税
◆相続時清算課税制度はこうやって活用する
◆相続時清算制度で失敗しがちな点
◆住宅資金贈与の特例で3000万円まで非課税
◆非課税枠を無理して使うのは本末転倒
◆教育資金贈与の特例で1500万円まで非課税
◆学習塾や水泳教室の学費も500万円まで非課税
◆教育資金贈与が少しずつリニューアル
◆結婚・子育て資金の贈与も1000万円まで非課税
◆ペットのための贈与という選択肢
◆ペット信託や保険のサービスも
◇◇特別2大企画◇◇
【生前・死後のチェックリスト65】
【家族が困らない かんたんエンディングノート】
AI端的にまとめて
ここいら得意そうなので
聞いてみます
以下に、提示された情報を箇条書きで整理しました。
【第1章:手続きで得する】
- 老親・老配偶者が亡くなった場合、提出する主な書類は公的書類。
- 手続き費用は10万円程度で、司法書士等専門家の活用も推奨。
- 国や自治体から積極的に知らされない「公的な給付金」が存在。
- 生前の話し合い不足は「争続(争族)」を招くリスクあり。
- 財産を相続する法定相続人を明確にしておく必要がある。
- 離婚・再婚を繰り返した家庭では相続トラブルのリスクが高い。
- 死後は現金不足(現金貧乏)に注意。
【第2章:得するもらい方(基本的な相続特例)】
- 配偶者および子供には相続税の非課税枠が存在。
- 基礎控除を理解して相続税を計算する(相続税の最高税率は55%)。
- 預金をスムーズに相続する方法と注意点がある。
- 生命保険金は一定額まで非課税、また一時所得として受け取る裏ワザも存在。
- 不動産の相続評価額は特例により大幅減額可能(例:小規模宅地等の特例)。
- 非上場株式や農地には納税猶予の特例制度あり。
- 遺言書の作成・活用が重要。
【第3章:得する9大改正(2020年版)】
- 「配偶者居住権」の新設で子供も有利に。
- 自筆遺言書を法務局で保管可能に。
- 遺留分の現金払いが可能となり不動産乗っ取りを防止。
- 「特別の寄与制度」で献身的介護者(非親族)への救済措置。
- 凍結口座から最大150万円の引出が可能に。
- 配偶者への生前贈与で自宅を相続財産から除外可能に。
- 財産処分のルール見直しと遺言書作成が簡略化。
- 遺言書効力見直し、不動産登記を迅速に。
【第4章:生前贈与が最高に得】
- 贈与税は年110万円まで非課税(暦年贈与)。
- 夫婦間贈与は2000万円まで非課税。
- 相続時精算課税制度を利用する際は注意点がある。
- 住宅資金贈与は特例で最大3000万円まで非課税。
- 教育資金贈与は最大1500万円まで非課税(学習塾なども500万円まで対象)。
- 結婚・子育て資金の贈与は最大1000万円まで非課税。
- ペットへの生前贈与(信託や保険)という新たな選択肢も。
【特別企画】
- 生前・死後に役立つチェックリスト65項目。
- 家族が困らないための「かんたんエンディングノート」の推奨。
これらのポイントを押さえることで、相続や生前贈与のトラブル防止や有効な節税対策につなげることができます。
【参考元リンク】